堛椕朄恖婣梲夛慜巎亅屘崅嶳嬙嵠愭惗偺嬈愌

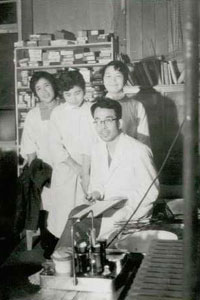

堛椕朄恖婣梲夛偺曣懱偱偁傞扥塇昦堾偼丄尦傪偨偩偣偽丄僼傽僀僶乕僗僐乕僾傕側偐偭偨偙傠偐傜屘崅嶳嬙嵠愭惗偑摉帪偲偟偰偼愭恑揑側宱暊堓嬀傗鋁惗専傪峴側偭偰偄偨嶳杒懞偺彫偝側姖晿偒偺恌椕強傪弌敪揰偲偡傞丅廬偭偰堛椕朄恖婣梲夛偺楌巎傪岅傞応崌丄偦偺慜巎偲偟偰崅嶳嬙嵠愭惗偺執嬈偵怗傟偞傞傪摼側偄丅
崅嶳嬙嵠愭惗偼戝惓俇擭俁寧偺惗傟偱丄堦崅偐傜愮梩堛戝偵擖妛偟丄徍榓侾俉擭偵懖嬈丅廔愴屻偟偽傜偔偼崙棫憡柾尨昦堾奜壢偵嬑柋偝傟偰偄偨偑丄徍榓俀係擭丄恄撧愳導懌暱忋孲嶳杒挰偱墱條偺偍晝忋偑奐嬈偝傟偰偄偨扥塇恌椕堾傪宲偄偱奐嬈偝傟偨丅
偦偙偱堦夘偺奐嬈堛偲偟偰抧堟偺堛椕偵実傢傞堦曽丄徍榓俁侽擭崰偐傜徚壔婍昦偺椪彴尋媶傪奐巒偟丄摉帪偼傑偩阾柧婜偲傕尵偊傞徚壔婍撪帇嬀偺尋媶傪巒傔丄偝傑偞傑側暘栰偱愭恑揑側尋媶偲椪彴墳梡傪峴傢傟偨丅傑偨撪帇嬀偩偗偱偼側偔丄摉帪埫崟偺憻婍偲尵傢傟偨鋁憻幘姵恌抐偵嵟傕憗偔偐傜庢傝慻傫偩妛幰偺堦恖偱偁傝丄偝傜偵宍懺揑側恌抐傗奜壢帯椕偩偗偱偼側偔丄抇鋁偺婡擻忈奞傗怘塧椕朄偵傕庢傝慻傒丄怱椕堛妛偵偍偄偰傕嬈愌偑懡偔丄慡恖揑堛椕傪幚慔偝傟偨愭惗偱偁偭偨丅
暯惉4擭偵崅嶳愭惗偑朣偔側傜傟偨屻丄偦傟傑偱柤梍夛挿傪堷偒庴偗偰偙傜傟偨恄撧愳徚壔婍昦堛妛夛偺6寧偺尋媶夛偺拞偱丄摿暿婇夋偲偟偰偦偺嬈愌偑乽宱暊堓嬀乿偺塮夋偲偲傕偵敪昞偝傟偨丅尵傢偽擔杮偺徚壔婍昦妛丄偍傛傃徚壔婍撪帇嬀妛偺塭偺楌巎偲傕尵偆傋偒崅嶳嬙嵠愭惗偺嬈愌撪梕傪偙偙偵宖嵹偡傞丅
屘崅嶳嬙嵠愭惗偺庡側巇帠
侾丏撪帇嬀娭學乮侾俋俆俉擭乣侾俋俇俇擭乯
丂丒捿傝忋偘幃暊峯嬀
丂丒宱暊堓嬀偵傛傞堓丒廫擇巜挵幘姵偺恌抐
丂丒捈挵塮夋朄
丂丒宱暊抇擷嬀
俀丏抇摴幘姵偍傛傃抇摴憿塭朄偵娭偡傞尋媶乮侾俋俇侽擭乣侾俋俈俇擭乯
丂丒暊峯嬀壓捈愙抇擷慂巋憿塭朄
丂丒抇擷撪帇嬀偲抇愇揈弌弍
丂丒捔醶嵻暪梡價儕僌儔僼傿儞惷拲抇摴憿塭朄
丂丒抇摴僕僗僉僱僕乕偺恌抐偲帯椕
俁丏鋁幘姵恌抐偵娭偡傞尋媶乮侾俋俇俁擭乣侾俋俈俁擭乯
丂丒鋁惗専朄偺奐敪
忋偵偁偘偨傛偆偵崅嶳愭惗偺巇帠偼徚壔婍昦慡斒偵傢偨傞傢偗偱偁傞偑丄摿偵弶婜偺巇帠偼擔杮偺徚壔婍撪帇嬀偺楌巎偲怺偔娭傢偭偰偄傞丅
傑偨偦傟埲奜偵傕徚壔婍昦幮夛曐尟尋媶夛側偳傪庡嵜偟丄曐尟恌椕忋偺夵妚傪捠偠偰抧堟堛椕傊偺徚壔婍昦恌椕庤媄偺晛媦偵恠椡偝傟偨丅偨偲偊偽徍榓37擭偵奐嵜偝傟偨戞1夞恄撧愳導徚壔婍昦尋媶夛偺僾儘僌儔儉傪尒傞偲丄乽撪帇嬀偲曐尟恌椕乿偲戣偟偨僔儞億僕僂儉傪巌夛偟丄導曐尟壽偺媄姱偲巟暐婎嬥扴摉姱傪抎忋偵忋偘偰偺僨傿僗僇僢僔儑儞傪峴側偭偰偄傞丅
埲壓偺昞偺嵍偑徚壔婍撪帇嬀敪揥偺楌巎丄塃偑偦傟偵娭傢傞崅嶳愭惗偺庡側巇帠偱偁傞丅
| 徚壔婍撪帇嬀偺楌巎偲 屘 崅嶳嬙嵠愭惗偺嬈愌 | ||||
| 惣楋 | 榓楋 | 悽奅偱偺撪帇嬀敪払巎 | 崅嶳嬙嵠愭惗偺巇帠 | |
| 1868 | 柧 1 | Kussmaul | 懱奜岝尮徹柧偵傛傞堓嬀 | |
| 1911 | 44 | Elsner | 峝幃堓嬀 | |
| 1922 | 戝 11 | Shindler | 峝幃堓嬀 | |
| 1932 | 徍 7 | Shindler | 擃惈堓嬀偺姰惉 | |
| 1934 | 9 | 嬎尨 | 崙嶻擃惈堓嬀偺惂嶌 | |
| 1948 | 23 | Segal | 擃惈堓嬀偵傛傞僇儔乕幨恀嶣塭 | |
| 1950 | 25 | 塅帯 | 堓僇儊儔嶣塭偵惉岟 | |
| 1953 | 28 | 嶈揷,忛強 | 堓僇儊儔偺椪彴墳梡奐巒 | |
| 1958 | 33 | 忢壀,嶳愳 | 暊峯嬀偺椪彴墳梡奐巒 | 幚抧奜壢堛偲暊峯嬀 |
| 1958 | 33 | Hirshowitz | 僼傽僀僶乕僗僐乕僾傪帋嶌 | 宱暊堓嬀偺奐敪偲椪彴墳梡 |
| 1960 | 35 | 俙俠俵俬 | 僼傽僀僶乕僗僐乕僾傪敪攧 | 宱暊堓嬀偵傛傞塮夋嶣塭 |
| 1960 | 35 | 僆儕儞僷僗 | 堓僇儊儔(GT-嘪)敪攧 | 廫擇巜挵偺撪帇嶣塭朄 |
| 1961 | 36 | 嶈揷,扥塇 | 嶣塭梡捈挵嬀 | 捈挵偺撪帇嶣塭朄 |
| 1962 | 37 | 擔徚妛夛 | 僼傽僀僶乕僗僐乕僾傪桝擖 | 惗専梡宱暊堓嬀偺巊梡 |
| 1963 | 38 | 挰揷惢嶌強 | 崙嶻僼傽僀僶乕僗僐乕僾帋嶌 | 宱暊抇擷撪帇朄 |
| 1964 | 39 | 挰揷惢嶌強 | 惗専梡僼傽僀僶乕僗僐乕僾姰惉 | |
| 1966 | 41 | 僆儕儞僷僗 | 僼傽僀僶乕僗僐乕僾晅堓僇儊儔(GTF-A) | |
| 1968 | 43 | 埌戲 懠 | 廫擇巜挵僼傽僀僷乕僗僐乕僾 | |


堓嬀偺楌巎偼1868擭偺 Kussmaul 偵巒傞偲偄傢傟偰偄傞偑丄尋媶揑偵偱傕椪彴墳梡偲尵偊傞偺偼 1932擭 Shindler 偺擃惈堓嬀偐傜偱偁傞丅偦偟偰1950擭偵偼栍栚揑偵堓撪偺嶣塭傪峴偆堓僇儊儔偑奐敪偝傟偨丅堦曽娞幘姵偵懳偟偰偼暊峯嬀偑幚梡壔偝傟丄偦偺椪彴墳梡偑奐巒偝傟偨偙傠丄嶳杒偺挰偺恌椕強偱惙傫偵暊峯嬀傪峴偭偰偄偨奜壢堛偑崅嶳愭惗偱偰偁偭偨丅
摉帪偺堓僇儊儔偼旕忢偵栍揰偑懡偔丄夋憸傕晄慛柧偱偁傝丄堦曽尰嵼偺撪帇嬀偺尨宆偱偁傞僼傽僀僶乕僗僐乕僾偼傑偩擔杮偱偼椪彴巊梡傕巒偭偰偄側偄帪戙偱丄僪僀僣偐傜Hirshowitz偺僼傽僀僶乕僗僐乕僾偑擔杮偵俀戜桝擖偝傟偨偽偐傝偱偁偭偨丅偙偺崰偵幚偼崅嶳愭惗偼搶戝偵偁傞堓嬀尋媶幰傪朘偹丄嫵偊傪岊偆偨偦偆偱偁傞偑丄偦偺帪偼乽揷幧偺恌椕強偺奐嬈堛偑傗傞偙偲偱偼側偄乿偲尟傕傎傠傠偵抐傢傜傟偨偲尵偆帠偱偁傞丅
偙偺帠偑偒偭偐偗偲側傝丄偦傟傑偱撈帺偱峴偭偰偄偨暊峯嬀偵傛傞堓撪晹偺娤嶡傪峫埬偟丄偦傟傪乽宱暊堓嬀乿偲偟偰敪揥偝偣丄扨側傞娤嶡偐傜偦偺摉帪偲偟偰偼悽奅揑偵傕夋婜揑偱偁偭偨僇儔乕塮夋嶣塭傗丄偦偺崰偱偼傑偩幚嵺偼扤傕惉岟偟側偐偭偨廫擇巜挵偺撪帇娤嶡丄捈帇壓惗専偵傛傞憗婜堓娻偺恌抐丄抇擷撪帇嬀側偳師乆偲妛夛敪昞傪峴偭偰偄偭偨丅
偟偐偟摉帪偼偙傟傜偡傋偰偺巇帠偑悽偺拞傛傝偁傑傝偵傕愭傫偠偰偄偨偙偲偱丄悽娫偐傜偼廫暘側棟夝傪摼偨偲偼尵偊側偐偭偨丅傗偑偰悽偺拞偼僼傽僀僶乕僗僐乕僾偺帪戙傊偲堏傝丄揹巕撪帇嬀偺弌尰偱崱傗宱暊堓嬀傪偼傞偐偵挻偊傞夋憸偲帯椕墳梡偑壜擻偲側偭偨丅
妛栤偺敪揥偺楌巎偼丄偦偺杮棳偐傜偩偗偱偼側偔丄偦傟傪懁柺偐傜巟偊丄墴忋偘偰偒偨懡偔偺愭払偺懚嵼傪敳偒偵偟偰岅傞偙偲偼弌棃側偄丅Shindler偺擃惈堓嬀偺嬯楯偲廗弉偑 Hirschowitz 偺僼傽僀僶乕僗僐乕僾偺挿強抁強傪晜挙傝偵偟丄堓僇儊儔偺惷巭夋憸偲宱暊堓嬀偺慛柧側摦揑塮憸偑崱擔偺傛傝棟憐揑側撪帇嬀傊偲寢傃偮偄偰偄偭偨偺偱偁傞丅
崅嶳愭惗偼偦偺屻丄擔杮徚壔婍昦妛夛摿暿夛堳丄擔杮徚壔婍撪帇嬀妛夛昡媍堳丄擔杮鋁憻昦尋媶夛塣塩埾堳丄抇摴幘姵尋媶夛姴帠丄徚壔婍俹俽俵尋媶夛姴帠側偳傪楌擟偝傟丄徍榓俆俇擭偐傜偼恄撧愳導徚壔婍昦堛妛夛夛挿丄徍榓63擭偐傜偼恄撧愳導徚壔婍昦堛妛夛偺柤梍夛挿偲偟偰嵟屻傑偱変乆偺巜摫偵偁偨傜傟偨偑丄暯惉係擭丄俈係嵥偺擭楊偵偰偛惱嫀偝傟偨丅
| 嶲峫暥專 | |
1)崅嶳嬙嵠丆徏懞棙抝丄暯堜徍揟幚抧奜壢堛偲暊峯嬀丂丂擔杮椪彴奜壢堛夛嶨帍.20:197,1959 |
11)崅嶳嬙嵠堓撪帇朄偺栍揰偺尋媶丂丂丂戞俀夞堓僇儊儔妛夛憤夛丂(1960) |
2) 崅嶳嬙嵠丄捯丂桾丄徏懞棙梇丄暯堜徍揟幚抧堛壠偵曋棙側暊暻彫愗奐捈恌朄丂丂丂擔杮椪彴奜壢妛夛憤夛(1959) |
12)崅嶳嬙嵠丄嶁杮岝峅丄捯丂桾丄塱悾晀峴帋嶌慻怐嵦庢梡宱暊堓嬀偺巊梡宱尡丂丂丂戞係夞擔杮撪帇嬀妛夛憤夛 (1962) |
3)崅嶳嬙嵠丄徏懞棙梇丄捯丂桾丄暯堜徍揟埨慡丄梕堈丄妋幚側娞僶僀僆僾僔乕朄丂丂丂擔杮椪彴昦棟妛夛丂乮1959乯 |
13)崅嶳嬙嵠丄嶁杮岝峅丄捯丂桾丄塱悾晀峴撪帇嬀偺岝尮偼傕偭偲嫮壔偡傋偒偱偁傞丅丂丂丂戞係夞擔杮撪帇嬀妛夛憤夛丂(1962) |
4)崅嶳嬙嵠丄徏懞棙梇丄捯丂桾丄暯堜徍揟暊暻彫愗奐捈恌朄乮戞堦曬乯丂丂丂丂乮娞抇摴幘姵廇拞抇愇徢偵墬偗傞墳梡乯 丂丂丂 擔杮徚壔婍昦妛夛憤夛(19xx) |
14)崅嶳嬙嵠宱暊堓嬀専嵏朄媦傃宱暊抇擷憿塭朄偵偮偄偰丂丂擔杮撪帇嬀妛夛戞係夞嬤婨抧曽夛(1963) 摿暿島墘 |
5)崅嶳嬙嵠暊暻彫愗奐捈恌朄乮戞擇曬乯丂丂丂擔杮徚壔婍昦妛夛(1960) |
15)丂Kiny aKoyamaA new approach to the diagnosis for the alimentary organs by means丂of Peritoneoscopeand other improved instrument Proc.1st cong. Int. Soc. Endoscopy ;520,1966 |
6)曅暯廳師丄崅嶳嬙嵠丄徏懞棙梇丄捯丂桾丄嶁杮岝帯丄暯堜徍揟暊暻彫愗奐捈恌朄乮戞嶰曬乯(庡偲偟偰16mm僇儔乕塮夋偵傛傞堓擲枌憸偺摦揑強尒偵廇偰) 丂丂擔杮徚壔婍昦妛夛憤夛丂(1960) |
16)崅嶳嬙嵠嵟嬤宱尡偟偨鋁墛條幘姵偵廇偄偰丂丂丂擔杮徚壔婍昦妛夛丂丂(1968) |
7)曅暯廳師丄崅嶳嬙嵠丄捯丂桾丄嶁杮岝帯丄徏懞棙梇丄暯堜徍揟暊暻彫愗奐捈恌朄乮戞巐曬乯丂丂乮庡偲偟偰椪彴揑宱尡偵婎偯偔彅峫嶡偵廇偰乯 丂丂 擔杮徚壔婍昦妛夛憤夛丂(1960) |
17)崅嶳嬙嵠抇鋁巹姶丂丂僋儕僯僔傾儞丂No.168 Page 13 1968 |
8)崅嶳嬙嵠丄嶁杮岝峅丄捯丂桾廫擇巜挵擲枌偺撪帇嶣塭朄偵偮偄偰丂丂丂(1960) |
18)崅嶳嬙嵠巹偺埑恌朄忋暊晹晄掕廌慽戜強愢偵傛傞僗僋儕乕僯儞僌朄 丂丂丂僋儕僯僔傾儞丂No.176丂Page 6丂1969 |
9)崅嶳嬙嵠丄嶁杮岝峅丄捯丂桾捈挵撪帇嶣塭偵墬偗傞奺庬撪帇嬀偺墳梡偵廇偄偰丂丂丂擔杮徚壔婍昦妛夛憤夛丂乮1960乯 |
19)崅嶳嬙嵠丄拞搰媊枦丄暯捤廏梇丄婽扟怶丄暉堜岝庻奐嬈堛偲堓惗専丂丂丂堓偲挵丂5:907-911,1970 |
10)崅嶳嬙嵠侾俇儈儕塮夋偵傛傞宱暊堓嬀恌抐偺宱尡丂丂戞俀夞堓僇儊儔妛夛憤夛丂(1960) |
20)崅嶳嬙嵠丄敽惛堦榊丄摗揷弒嶌丄涇尨泬丄塱悾晀峴鋁忈奞僗僋儕乕僯儞僌忋偺擇丄嶰偺栤戣偵廇偄偰丂丂 丂戞俁夞擔杮鋁憻昦尋媶夛(1973) |
仹250-0042丂恄撧愳導彫揷尨巗壃孍406丂TEL丗0465-34-3444
 宱暊堓嬀婰榐塮憸(栺2暘/1.6MB/壒惡柍偟)
宱暊堓嬀婰榐塮憸(栺2暘/1.6MB/壒惡柍偟)